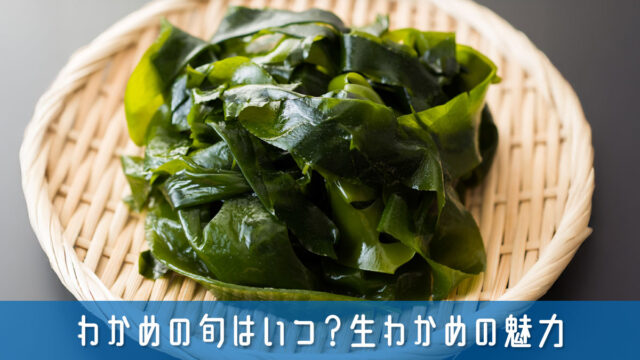鮎の塩焼きの内臓はどうすればいい?食べられるの?調理のポイントを解説

夏の風物詩「鮎の塩焼き」。パリッと香ばしい皮と、ふっくらとした身はたまりませんよね。しかし、内臓を食べるか捨てるか、悩んだ経験はありませんか?
鮎の塩焼きの内臓は食べても大丈夫?
この記事を読めば、鮎の内臓について知識を深めることができます。これまで内臓を捨てていた方も、この記事を読めば、鮎の塩焼きを丸ごと味わい尽くせるようになるでしょう。
この記事を参考にして、鮎の内臓を含めた美味しい塩焼きを楽しんでください。
鮎の塩焼きで内臓は食べられる?

鮎の塩焼きの内臓は食べられます。
秋刀魚(サンマ)の塩焼きと同様に、鮎の塩焼きも内蔵を食べることができます。鮎の内臓は、ほろ苦さと旨味が絶妙な味わいで、鮎の塩焼きをさらに美味しくしてくれます。特に天然の鮎の内臓は風味が良く、多くの人に親しまれています。
しかし、内臓の苦味が苦手な人や、養殖鮎を食べる場合は内臓を取って調理することもおすすめです。
養殖鮎の内蔵も食べられないわけではありませんが、天然の鮎に比べると風味などが劣ります。
塩焼きで内蔵まで食べる代表的な魚は鮎と秋刀魚です。

- 鮎(アユ)
- 秋刀魚(サンマ)
鮎や秋刀魚では、内臓(はらわた)を食べる人が多く、その苦味を「おいしい」と感じる文化があります。日本では古くから魚の内臓を味わう習慣があり、特に塩焼きとして楽しまれてきました。
内臓のほろ苦さと旨味は身の甘みを引き立て、多くの人に好まれています。日本人の味覚に根付いた食文化として、今も受け継がれているのです。

なぜ鮎の内臓は食べることができる?

鮎の内臓が食べられるのは、天然の鮎が主にコケ(藻類)などの植物性の餌を食べているからです。消化の良い植物性の餌によって、内臓には不快な苦味や臭みが少なく、寄生虫のリスクも比較的低いため安心して味わえます。
天然鮎の内臓には特有のほろ苦さと香りがあり、身の甘みと絶妙に調和することで鮎全体の美味しさを引き立てます。この風味は「日本の夏の味覚」として塩焼きで楽しまれ、頭から尻尾まで丸ごと食べる文化を生み出してきました。
一方で養殖鮎は事情が異なります。養殖過程で与えられる餌には魚粉など動物性成分が多く含まれることがあり、その影響で内臓に独特の臭みが出やすくなります。そのため、養殖鮎では内臓を取り除いて調理することも一般的です。
つまり、天然鮎の内臓は植物性の食性に由来する澄んだ風味が魅力であり、養殖鮎では餌の影響によって風味が変化しやすいという違いがあるのです。
十分な加熱をして内臓の中心までしっかり火を通しましょう
秋刀魚も塩焼きで内蔵を食べる代表的な魚
秋刀魚は塩焼きで内臓まで食べられる代表的な魚で、秋の味覚として長く親しまれてきました。内臓特有のほろ苦さが身の旨味を引き立て、丸ごと味わう楽しみを生み出しています。
秋刀魚が内臓まで食べやすい理由の一つは、「無胃魚(むいぎょ)」に分類される点にあります。胃を持たないため、餌は食道から腸へ直接送られ、消化・吸収されたのち速やかに排出されます。この仕組みによって内臓に有害物質や強い臭みが残りにくく、美味しく食べられるのです。
さらに、内臓のほろ苦さは大人の味覚として好まれ、脂がのった身の甘みと調和することで奥行きのある味わいを生みます。そのため、日本の食文化において秋刀魚の塩焼きは「頭から尾まで丸ごと楽しむ料理」として受け継がれてきました。
参考:秋刀魚のはらわたは食べるべき?美味しい食べ方と注意点を詳しく解説

鮎の大きさによっては頭から丸ごと食べることができる

鮎は大きさによって、頭から丸ごと食べられる魚です。特に小ぶりの若鮎や稚鮎は骨や頭がやわらかく、焼き加減を工夫すればそのまま全部食べることができます。
鮎を頭から丸ごと食べるときの注意点
鮎の大きさ
小ぶりな鮎の方が、頭から丸ごと食べやすいです。
- 小さい鮎ほど骨や頭がやわらかいため、口に入れたときに違和感が少ない
- 成魚や大きめの鮎は頭や骨が硬く、喉につまる危険がある
- 丸ごと食べられるのは体長15cm程度までが目安
丸ごと食べるなら、小さめの鮎を選ぶのが安全で美味しく楽しめるコツです。
焼き具合
しっかり焼けている鮎であれば、頭や骨も香ばしく食べやすくなります。頭から食べたい場合は、時間をかけてよく鮎を焼きましょう。
おすすめの時期
6月〜7月の若鮎の時期が、丸ごと食べやすくおすすめです。
- 若鮎は成長途中のため、骨や頭がやわらかい
- 脂も少なく、全体的に軽やかな味わい
- 内臓の苦味も控えめで食べ慣れていない人に向いている
初めて鮎を丸ごと食べるなら、6〜7月の若鮎を選ぶと安心して楽しめます。
鮎の内臓は苦味と旨味が織りなす大人の味わい

鮎の内臓は独特のほろ苦さと豊かな旨味が特徴で、身の甘みと絶妙に調和します。このコントラストによって鮎全体の味に奥行きが生まれ、特に塩焼きでは格別の美味しさを堪能できます。
内臓には旨味成分が豊富に含まれており、加熱することでその旨味が引き出されます。淡泊な身と濃厚な内臓の風味が合わさることで、鮎ならではの深い味わいを楽しめます。
さらに、内臓のほろ苦さは日本酒との相性が抜群で、大人の味覚を満足させる要素にもなります。鮎を丸ごと味わうことで、身と内臓が織りなす調和の妙を存分に体験できるのです。
酸味には苦味を和らげる効果があるため、鮎の内臓が苦手な方も、蓼酢(たです)につけたり、すだちを絞ったりすることで、苦味がやわらぎ、食べやすくなります。
参考:鮎の塩焼きが美味しくなる!蓼酢の代わりになるオススメの食材と調味料

安全に食べるための注意点
鮎の内臓を安全に食べるためには、十分な加熱調理と衛生的な取り扱いが必要です。十分な加熱調理が、寄生虫のリスクを避け、美味しく安全に鮎の内臓を楽しむことができます。家庭でもプロのような注意を払って調理し、安全に美味しい鮎の内臓を味わいましょう。
- 十分な加熱調理
十分に加熱することで、寄生虫のリスクを避けることができます。焼く場合は、中心部までしっかりと火を通すことが重要です。内臓の生食は避けるべきです。 - 衛生的な取り扱い
鮎を調理する際には、調理器具や手をよく洗うことが重要です。これにより、二次的な汚染を防ぐことができます。
鮎の寄生虫について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
参考:鮎の刺身は大丈夫?寄生虫の危険性とリスクを抑える予防策を徹底解説

天然鮎の内臓がジャリジャリする?
天然鮎は内臓がジャリジャリする場合があります。
主な原因は以下です。
- 川の濁りの影響
- ダムの放水の影響
- 餌の藻を食べる時の影響
中でも、ダムの放水の影響が関係しているといわれます。
鮎ってどんな魚?

鮎は清流を好む川魚で、日本では古くから親しまれてきた食材です。夏が旬とされ、鮎の塩焼きは季節を象徴する料理として広く愛されています。
清らかな流れで育った鮎は爽やかで独特の香りと上品な味わいを持ち、その香りの良さから「香魚」とも呼ばれています。特に塩焼きにすると川魚ならではの香ばしさと淡泊な身の旨味が際立ち、夏の食卓を彩ります。
さらに鮎は食材としてだけでなく、日本の釣り文化とも深く関わっています。代表的なのが伝統漁法「友釣り」で、多くの釣り人に楽しまれ、鮎を通じた季節の風物詩としても受け継がれています。こうした食と文化の両面で、鮎は日本人にとって特別な存在となってきました。
天然の鮎の生態と分布
天然の鮎は日本各地の川に広く分布し、一年で一生を終える「一年魚」として知られています。秋に川で産卵・孵化した稚魚は一度海や河口域に下り、冬を越したのち春から初夏にかけて成長して川へ戻ります。
その後、中流から上流域で生活し、川底の石についた藻類を主に食べて育ちます。
この藻類こそが鮎特有の香りと風味を生み出す要因であり、鮎が「香魚」と呼ばれるゆえんです。さらに清流の環境や地域ごとの藻類の質が味に影響するため、土地ごとに微妙な風味の違いが生まれます。
こうした自然条件の違いが、天然鮎の奥深い味わいと魅力を一層際立たせています。

天然の鮎はスイカやキュウリのような独特の香りがします。
鮎と同じように海へ下ってから川に戻る魚の代表例に「鮭」があります。両者は川で生まれ、海へ下り、再び川に戻るという共通点を持ちますが、成長の過程に大きな違いがあります。
鮭は海で長期間成長して体を大きくし、その後産卵のために川を遡上して寿命を迎えます。この生活史は「遡河回遊(そかかいゆう)」と呼ばれます。対して鮎は、海から川へ戻った後も成長を続けるのが特徴です。
川に戻った鮎は川底の石についたコケ(藻類)を食べて体を大きくし、このような生活史は「両側回遊(りょうそくかいゆう)」と呼ばれています。
つまり、鮭と鮎はいずれも川と海を行き来しますが、鮭は海で成長し、鮎は川で成長を続けるという点が両者を区別する大きな特徴となっています。
| 鮎 | 両側回遊(りょうそくかいゆう) |
|---|---|
| 鮭 | 遡河回遊(そかかいゆう) |
鮎の稚魚放流

鮎の稚魚放流は、人工的に孵化させた稚鮎や琵琶湖産の鮎を川に放流することで、自然の川で育てる取り組みです。放流は、乱獲や河川環境の悪化によって減少した鮎の数を回復し、未来の豊かな漁獲量を確保することを目的としています。
個体数の維持
近年、鮎は乱獲や河川環境の変化によって個体数が減少しています。水質の悪化やダム建設による生息環境の分断なども影響し、自然繁殖だけでは十分に数を維持できない状況が続いています。
この問題を補うために行われているのが稚魚の放流です。養殖施設で育てた稚魚を河川に放つことで、自然繁殖が不十分な年でも個体数を安定させることができます。放流は釣り資源を守るだけでなく、地域の漁業や観光を支える役割も担っています。
一方で、放流に依存しすぎると遺伝的多様性の低下や自然環境への影響が懸念されます。そのため近年では、産卵場の保全や河川環境の改善といった取り組みも並行して進められており、持続的に鮎を守るための努力が続けられています。
地域経済への貢献
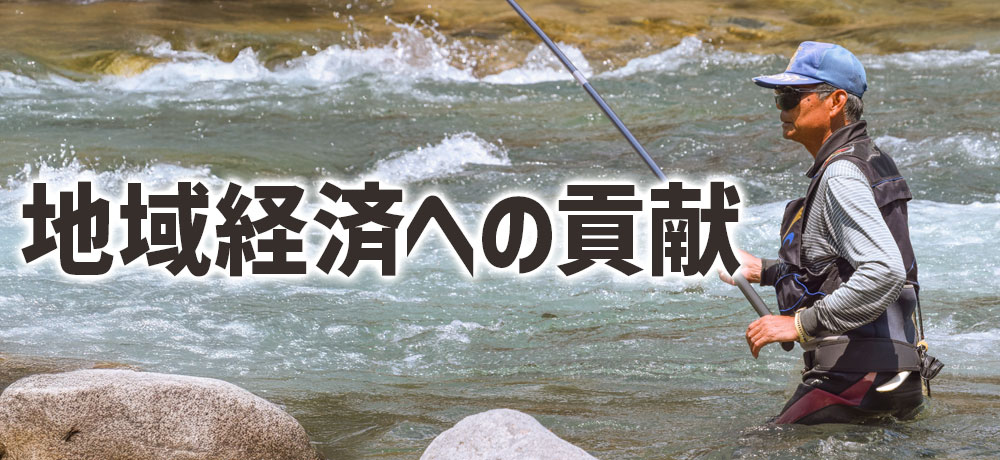
鮎の友釣りは、日本各地で重要な観光資源となっています。清流を舞台に行われる友釣りは、独特の漁法として釣り人を惹きつけ、毎年多くの人々が川を訪れます。
この背景には稚魚放流の取り組みがあります。放流によって鮎の個体数が安定し、十分な釣り資源が確保されることで釣り人が集まりやすくなります。結果として、地域の観光や経済活動の活性化につながります。
宿泊施設や釣具店、飲食店などはその恩恵を大きく受けます。釣り客が宿泊や食事を楽しみ、地元の特産品を購入することで、地域全体の収益が増加します。さらに、鮎料理を提供する飲食店は観光の魅力を高め、地域ブランドの発信にも貢献しています。
このように、友釣りは単なる釣りの楽しみにとどまらず、観光・経済・文化の面で地域社会を支える存在となっています。
養殖の鮎

養殖の鮎は、自然繁殖では得られない安定した供給を実現するために人工的に育てられた鮎です。均一なサイズ、安定した品質、通年供給が特徴で、料理や市場での人気を支えています。
- 均一なサイズと品質
- 安定した供給
- 衛生管理
- 餌の管理
均一なサイズと品質
養殖の鮎は、管理された環境で育てられるため、サイズや品質が均一です。これにより、料理する際に一定の品質が保証されるため、飲食店や家庭での利用に適しています。
安定した供給
自然の環境に依存しないため、年間を通じて安定した供給が可能です。自然繁殖の鮎は季節や環境に影響されやすいため、養殖による供給の安定性は市場の需要を満たす上で重要です。
衛生管理
養殖場では、鮎の健康状態や水質の管理が徹底されているため、病気や寄生虫のリスクが低減されています。このため、安全に消費できる点が消費者にとって大きなメリットです。
餌の管理
養殖の鮎は、栄養バランスが考慮された餌を与えられるため、健康的に育ちます。餌には魚粉や植物性の成分が含まれており、これが鮎の成長を助けます。
天然の鮎と養殖の鮎の比較
| 天然鮎 | 養殖鮎 | |
|---|---|---|
| 旬 | 夏(6月〜10月) | 年間を通して |
| 味 | 独特の風味と上品な味わい | 脂が乗っていて、淡白 |
| 香り | ほとんどなし | スイカやキュウリの香り |
| 価格 | 高価 | 比較的安価 |
- 天然の鮎は急流の中を泳ぐので、養殖鮎に比べてヒレが大きいです。
- 天然の鮎は口を大きく開けて藻を食べるので、顔周りがシャープです。
- 養殖鮎は内臓脂肪が多いです
琵琶湖の鮎

琵琶湖の鮎は、大きく成長せず、海に下ることもありません。これは琵琶湖の独自の生態系と地理的特性によるものです。
成長の限界
琵琶湖の鮎は、湖の中で一生を過ごすため、成長の限界があります。琵琶湖での鮎の餌はプランクトンであるため、河川にいる鮎に比べ、コケ(藻)などを食べないため10cmほどにしか大きくなりません。
琵琶湖の鮎は「小鮎」とも呼ばれ、その名の通り小さいままの状態で成長します。小鮎は、サイズが小さく、骨まで食べられるため、塩焼きや天ぷら、佃煮、南蛮漬けにして楽しむことが多いです。
琵琶湖の鮎も他の河川へ放流したり、養殖をすると、大きく成長します。
海に下らない理由
琵琶湖の鮎は「陸封型」と呼ばれ、湖の中で一生を過ごします。これは、琵琶湖が内陸の閉鎖水域であるため、海へのアクセスがないことに起因しています。
通常、鮎は川を下って海に行き、再び川を遡上して成長しますが、琵琶湖の鮎は海に下ることがありません。
塩焼きに最適な鮎の選び方

鮎の塩焼きを美味しく仕上げるためには、鮮度が非常に重要です。新鮮な鮎を選ぶことで、身の甘みや内臓の風味を最大限に楽しむことができます。
- 目が澄んでいる
新鮮な鮎は目がクリアで光沢があります。くすんでいたり、白濁している場合は避けた方が良いでしょう。 - エラが鮮やかな赤色をしている
新鮮な鮎は、エラが鮮やかな赤色をしています。 - 体に張りがある
鮎の体を軽く押したときに弾力があり、元の形に戻るものが新鮮です。触ったときに柔らかいものは鮮度が落ちている可能性があります。 - 魚臭さが少ない
新鮮な鮎は川魚特有の爽やかな香りがします。魚臭さが強い場合は鮮度が低いことが多いです。
鮎の塩焼きの作り方

塩焼きの下準備
鮎の塩焼きを美味しく仕上げるためには、下準備が非常に重要です。正しい下準備をしっかりと行うことで、鮎の風味を最大限に引き出し、焼き上がりが格段に良くなります。
家庭でも簡単にできる方法なので、ぜひ試してみてください。
ぬめり取り
鮎の表面にはぬめりがあるため、これを取り除くことで焼いたときの風味が良くなります。塩を使ってぬめりをこすり取り、流水で鮎を洗う方法が一般的です。
もしくは、包丁を使って尾の方から頭に向かってヌメリをこそげ取ってください。この場合は、ウロコも同時に取ることができます。
フン出し
鮎の体内に排泄物が残っている場合があるので、お腹を頭の方から肛門にむかって、手で押して、残っている排泄物を取り除いてください。排泄物が残っていると、雑味や生臭みのもとになります.
この工程は大事です
内臓の処理
鮎の内臓は食べることができますが、苦味が気になる場合は取り除くことをおすすめします。
水分を拭き取る
下処理が終わったら余計な水分は拭き取りましょう。余計な水分を拭き取ることで、焼き上がりがきれいに仕上がります。
家庭で作る鮎の塩焼きの作り方

家庭で鮎の塩焼きを作るためには、鮮度の良い鮎を選び、丁寧に下処理を行い、均一に塩を振ってじっくりと焼くことが大切です。これにより、外はカリッと、中はふっくらとした美味しい鮎の塩焼きを楽しむことができます。
均一に塩を振る
鮎全体に均一に塩を振ることで、焼き上がりの味が均一になります。塩は「化粧塩」といって、背びれや腹びれにやや多めの塩を振る(付ける)ことが重要です。化粧塩をすることで、背びれや腹びれの焦げ付きを防ぎ、見た目も美しくなります。
焼き方のコツ
炭火を使うと香ばしく焼けますが、家庭用のグリルでも美味しく焼けます。中火でじっくりと焼くことで、外はカリッと、中はふっくらと仕上がります。
家庭で塩焼きで内蔵を食べる注意点
家庭用のグリルで鮎の塩焼きを作り、内臓まで美味しく食べたい場合は、15〜20cm前後の比較的小ぶりな鮎を使うのがおすすめです。大きすぎる鮎は火の通りが不十分になりやすく、特に内臓部分が半生になるリスクが高まります。
安全で風味よく仕上げるためには、調理工程でひと工夫加えることが重要です。その代表的な方法が「お腹に切り込みを入れる」ことです。鮎は丸ごと焼くのが一般的ですが、そのままだと内臓に火が十分通らない場合があります。
腹側に浅く切り込みを入れることで熱が中心部まで届きやすくなり、均等に火が通るようになります。見た目を大きく損なうことなく、味や香りを保ちながら安全性を高められるのがこの工夫の利点です。
特に鮎の内臓は独特のほろ苦さと旨味が特徴で、しっかりと火を通すことで安心して楽しむことができます。寄生虫のリスクを避けるためにも、生焼けには注意し、十分に加熱することが大切です。
参考:鮎の刺身は大丈夫?寄生虫の危険性とリスクを抑える予防策を徹底解説

鮎の塩焼きは炭火が最高です

鮎の塩焼きを美味しく仕上げるには、炭火で焼くのが最も適しています。炭火で焼くことで、外はカリッと香ばしく、中はふっくらジューシーに仕上がり、鮎の旨味を最大限に引き出すことができます。
炭火焼きには、他の調理法にはない特有のメリットがあります。炭火の持つ遠赤外線効果が、鮎を均一に焼き上げるため、皮はパリッと、身はふんわりとした食感が楽しめます。
炭火の遠赤外線効果
炭火は、遠赤外線を放射することで、鮎の内側からじっくりと焼き上げます。これにより、鮎の身が乾燥しすぎることなく、ジューシーな仕上がりになります。
一方で、皮の部分はしっかりと焼き目がつき、パリッとした食感が生まれます。鮎の内側にも火が入りやすいため、鮎の内臓(はらわた)にも火が入りやすくなります。
余分な脂が落ちる
鮎は脂がのっている魚ですが、炭火で焼くと余分な脂が自然に落ち、魚自体が軽やかな仕上がりになります。
脂が落ちることで、身がくどくならず、ちょうど良いバランスで脂の旨味が残ります。また、落ちた脂が炭に触れることで香ばしい香りが立ち、鮎全体を包み込みます。
炭の香ばしい風味と燻煙の風味
炭火で焼くと、炭特有の香りが鮎にほんのりと移り、鮎に独特の香ばしさが加わります。また、鮎の脂が炭に落ちることで、燻煙が発生し燻煙の風味が鮎に移り、鮎が香ばしくなります。
炭火で焼く、焼き鳥も同じです。
この香りが、塩焼きのシンプルな味付けをより引き立て、鮎の風味をさらに豊かにします。
均一な火加減
炭火は、安定して強い火力を保ちながらも、遠赤外線の効果でじっくりと均等に加熱します。そのため、鮎全体が均一に火が通り、外側が焦げすぎることなく、身の部分もしっかりと火が入ります。
グリルやフライパンでは得られない、この均一な焼き上がりが、炭火焼きの大きな利点です。
鮎の塩焼きを蓼酢で味わう
鮎の塩焼きをさらに美味しく楽しむ方法の一つに、蓼酢(たでず)を使うことがあります。蓼酢の爽やかな酸味と辛味が、鮎の旨味を引き立て、特に夏の季節にはさっぱりとした風味が食欲をそそります。
蓼酢の材料は一般的にヤナギタデの葉が使われます。ヤナギタデは蓼科の一年草で、水辺などに自生する植物です。独特な辛味があり、これが蓼酢に特有の風味と爽やかさを生み出します。
参考:鮎の塩焼きが美味しくなる!蓼酢の代わりになるオススメの食材と調味料

鮎の内臓の伝統的な食文化

日本では古くから、鮎の内臓を食べる文化があります。その代表的な食文化の一つが「うるか」です。「うるか」は、鮎の内臓を塩漬けにして発酵させた日本の伝統的な保存食です。
特に、鮎が豊富に獲れる地域で古くから親しまれています。内臓の独特な苦味と塩味が特徴で、独特の風味と食感があり、日本酒やご飯のお供として好まれています。
- 苦うるか
鮎の内蔵だけを塩漬けにしたもので、特有の苦味があります。 - 身うるか
鮎の身と内臓を一緒に塩漬けにしたもの。一般的で、旨味と香りが特徴です。 - 子うるか
鮎の卵巣だけを塩漬けにしたもの。上品な味わいで、人気があります。 - 白うるか
鮎の精巣だけを塩漬けにしたもの。濃厚な味わいで、酒の肴によく合います。
鮎の正しい冷凍保存と解凍の手順

鮎を冷凍保存・解凍することで、鮮度を保ちながら長期保存が可能になります。正しい方法で冷凍・解凍すれば、ある程度の保存が可能です。冷凍保存期間は、約2週間〜4週間を目安にしてください。
家庭で冷凍した鮎は、解凍後の生食を避けるべきです。
家庭用冷凍庫では、急速冷凍ができないため、鮮度が低下しやすくなります。
鮮度が低下した鮎は、生食すると食中毒のリスクが高まります。
- 天然鮎は加熱調理してから食べる
天然鮎は、必ず加熱調理してから食べるようにしましょう。加熱調理することで、寄生虫を死滅させることができます。 - 養殖鮎も生食は避ける
養殖鮎は、寄生虫の少ない環境で育てられているため、生食も比較的安全です。ただし、家庭で冷凍した場合は、鮮度低下や衛生面のリスクがあるため、生食は避けた方が無難です。 - 冷凍鮎は調理してから食べる
冷凍鮎は、解凍後に必ず加熱調理してから食べるようにしましょう。
鮎の冷凍保存方法
- 鮎を洗う
鮎の内臓を取り除き、流水でよく洗い、表面のぬめりや汚れを落とします。 - 水気を拭き取る
キッチンペーパーなどで鮎の水気をしっかりと拭き取ります。 - ラップで包む
一尾ずつラップで包みます。 - 冷凍保存袋に入れる
ラップで包んだ鮎を冷凍保存袋に入れ、空気を抜いて密封します。 - 冷凍庫に入れる
鮎を冷凍庫に入れます。
冷凍焼けを防ぐために、密閉できる保存袋を使用してください。
冷凍焼け
冷凍焼けは、食品中の氷結部分が乾燥し、風味が損なわれたり、食感が悪くなったりする現象です。
鮎の解凍方法
- 冷蔵庫で解凍
冷凍庫から取り出した鮎を、冷蔵庫に移してゆっくり解凍します。 - 流水解凍
時間がない場合は、流水解凍することもできます。流水を当てながら、鮎を解凍します。 - 電子レンジ解凍
電子レンジ解凍は、風味や食感が損なわれる可能性があるため、おすすめしません。
解凍後は、速やかに調理し、再冷凍は避けましょう。
再冷凍すると、品質が低下し、味が損なわれる可能性があります。
鮎の塩焼きの内臓はどうすればいい?:まとめ
この記事では、鮎の塩焼きと内臓について詳しく説明しました。鮎の内臓は、その独特の苦味と旨味が特徴で、正しい処理と調理法を知ることで安全に美味しく楽しむことができます。
この記事では以下のポイントについて解説しました。
- なぜ鮎の内臓は食べることができるのか
- 鮎の基本情報(天然の鮎、養殖の鮎、琵琶湖の鮎)
- 鮎の内臓の苦味と旨味の味わい
- 塩焼きに最適な鮎の選び方
- 家庭で作る鮎の塩焼き
この記事を通じて、鮎の塩焼きと内臓についての理解が深まったと思います。鮎の内臓を正しく処理し、安全に調理することで、鮎の持つ本来の旨味を最大限に引き出すことができます。
鮎の塩焼きは、内臓まで美味しく食べられる奥深い料理です。ぜひ今回ご紹介した方法で、鮎を余すことなく味わってみてください。