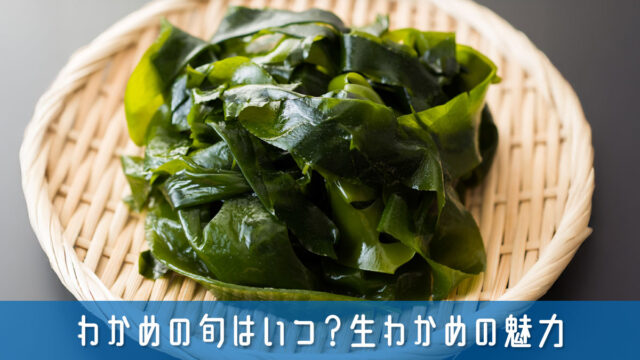うなぎの旬って夏じゃないの?天然と養殖でまったく違うその理由

「うなぎの旬」と聞いて、多くの人が真っ先に思い浮かべるのは「夏の土用の丑の日」かもしれません。確かにこの時期は、スーパーや飲食店でうなぎの蒲焼がズラリと並び、季節の風物詩として定着しています。
実は「うなぎの旬」は、天然と養殖でまったく違うのです。
天然うなぎの旬は、秋から冬。冬眠を控えて脂をたっぷり蓄えたこの時期のうなぎは、格別の味わいがあります。一方、養殖うなぎは人工的に育てられているため、季節に関係なく品質が安定しています。
特に「夏=うなぎ」というイメージは、江戸時代に仕掛けられた販促戦略がきっかけだったことをご存じでしょうか?
この記事では、そんな「うなぎの旬」について、天然と養殖の違いをわかりやすく解説します。
うなぎの旬っていつ?天然と養殖でどう違う?

うなぎの旬と聞いて、多くの人が「夏」と思い浮かべるかもしれません。確かに、土用の丑の日は夏にあります。しかし、うなぎと養殖うなぎでは「旬」の時期がまったく異なります。
| 観点 | 内容 |
|---|---|
| 味 | 一番おいしい時期。旨みや香りが濃くなる |
| 栄養 | 成分が最も豊富になる時期。ビタミンや脂質が高まることが多い |
| 値段 | 出回る量が多くなるため、比較的手頃な価格で手に入る |
| 季節感 | 旬の食材を食べることで「季節」を感じる楽しみがある |
「旬(しゅん)」とは、ある食材が最も美味しく、栄養価も高くなる時期のことを指します。自然のリズムに合わせて、その食材が育ち、味や香り、食感が最も良い状態になるタイミングです。
天然うなぎの旬は秋から冬

天然うなぎの旬は、晩秋から初冬です。
天然のうなぎは、冬になる前に脂をたっぷり蓄えます。これは、冬眠や産卵のために体力をつける自然の本能によるものです。そのため、秋から冬にかけてのうなぎは、身が引き締まり、脂のりが最も良い状態になります。

天然うなぎを一番おいしく食べたいなら、秋から冬がベストシーズンです。
天然うなぎの特徴

天然うなぎは、身が引き締まり風味が濃く、野性味があります。
自然の川や湖で育った天然うなぎは、流れの中で泳ぎ回るため筋肉質です。また、餌も自然の小魚や虫を食べているため、養殖うなぎにはない深い風味を感じられます。
さらに、天然うなぎは一生のうちに川から海へ下って産卵し、ふたたび川へ戻ってくるという独特の回遊性を持っています。この生き方が、身の引き締まりや風味の力強さにつながっています。
天然うなぎは、引き締まった肉質と香り高い味わいが魅力です。
天然うなぎ=美味しいとは限りません。天然ものは育った環境によって水質の影響を受けやすく、産地によっては独特の臭みがあることもあります。そのため、人によっては食べ慣れている養殖うなぎの方がクセが少なく、むしろ美味しく感じる場合もあります。
養殖うなぎの旬は夏?“土用の丑の日”に合わせている

養殖うなぎの旬は“需要”に合わせた夏(6月〜8月)とされます。
夏の土用の丑の日に合わせて、流通業者や生産者が出荷のピークを調整しています。「うなぎ=夏」のイメージが定着しているため、その需要に合わせて準備されているのが養殖うなぎです。

養殖うなぎの旬は“夏”とされることが多いですが、実際には一年を通して美味しく食べられます。
「旬」とは自然界における最も美味しい時期を指す言葉ですが、養殖うなぎは人工的に育てられているため、季節に関係なく品質を安定させることが可能です。具体的には、以下のような管理が行われています。
- 水温を20〜28℃の間で管理することで、うなぎが最も活発に成長する環境を保つ
- 餌の種類や量を調整することで、脂ののりや身のやわらかさをコントロールできる
- 出荷のタイミングを調整し、常に最適な状態で市場に供給することが可能
そのため、スーパーや飲食店で提供される蒲焼などのうなぎ製品は、季節を問わず美味しく仕上がっています。

「夏=うなぎ」のイメージは根強いですが、養殖技術の進化により、私たちは一年中おいしいうなぎを楽しめる時代に生きています。
養殖うなぎの特徴
養殖うなぎは脂が均一にのっていて、味にムラがなく安定しています。
水温管理や餌の種類をコントロールできるため、一定の品質で出荷できます。特に脂のりを重視して育てることで、柔らかくとろけるような食感になります。
安定した品質と食べやすさを求めるなら、養殖うなぎが最適です。
土用の丑の日とうなぎの関係を深掘り
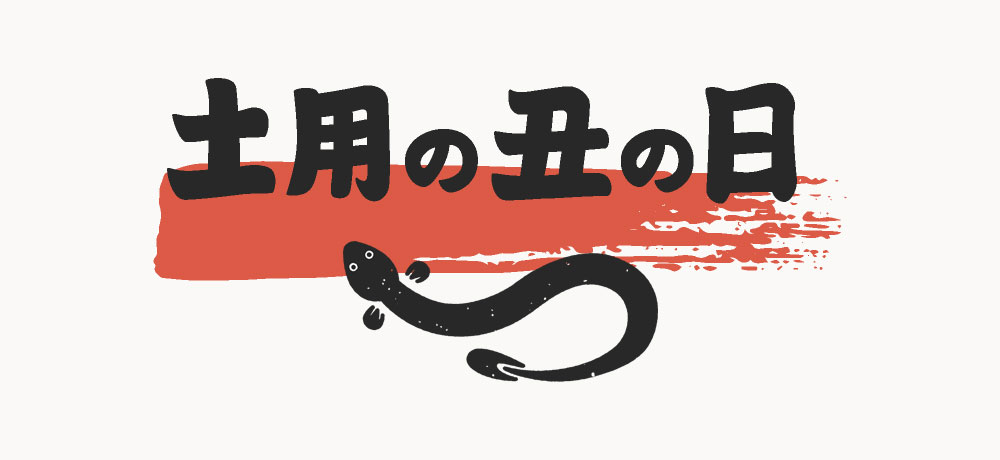
「うなぎ=夏」というイメージの背景には、古くからの風習や知恵があります。特に「土用の丑の日」にうなぎを食べる習慣は、多くの人にとって夏の風物詩のひとつです。ここでは、その起源や理由を歴史と栄養の両面から詳しく掘り下げていきます。
平賀源内が夏のうなぎブームを作った背景
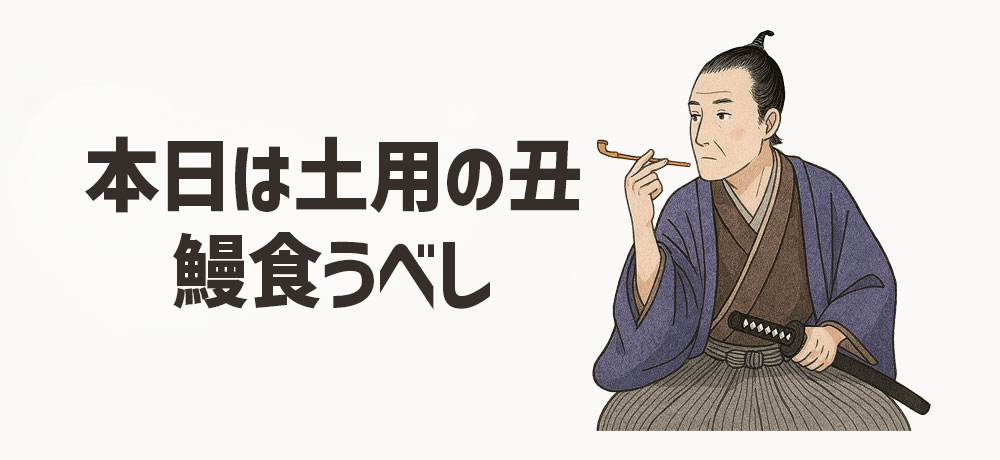
「土用の丑の日にうなぎを食べる」習慣は、江戸時代の学者・平賀源内によって広まった商業的な工夫がきっかけです。
江戸時代、夏になるとうなぎはあまり売れなくなっていました。あるうなぎ屋が相談を持ちかけたところ、平賀源内は源内は「本日は土用の丑、鰻食うべし」と書いた看板を出すことを提案しました。この宣伝が功を奏し、多くの客が訪れたといわれています。
「土用の丑の日にうなぎ」という習慣は、江戸のアイデアマンによる販促戦略が始まりでしたが、現代では日本の夏を象徴する文化となっています。
「土用の丑の日」については、以下の記事でくわしく解説しています。

夏のうなぎのスタミナ効果

うなぎは夏バテ予防に役立つ栄養が豊富に含まれています。
うなぎには、ビタミンA・B群、D、Eに加え、タンパク質やDHA、EPAといった栄養素がバランスよく含まれています。特にビタミンB1は、疲労回復に効果があるとされ、夏のだるさや食欲不振に有効です。
うなぎは季節の習慣だけでなく、理にかなった栄養食です。夏の疲れやすい時期にこそ、積極的に取り入れる価値があります。
一度は食べてみたい 「新仔うなぎ」のとろける食感

「新仔うなぎ」は、うなぎの中でも特にやわらかく、とろけるような食感が魅力です。
新仔うなぎ(しんこうなぎ)とは、シラスウナギから半年~1年未満で育てられ成鰻サイズに育てられた若いうなぎです。
天然うなぎは、成鰻サイズになるまで3〜5年かかります
新仔うなぎは、成長して日が浅いため、身はやわらかく、脂のノリも軽やかです。筋肉の繊維は細く、骨も柔らかいため、口の中でほぐれるように広がります。
通常のうなぎとはまったく異なる、その繊細な美味しさをぜひ体験してほしいです。
うなぎの旬は天然と養殖で違う理由:まとめ
この記事では、「うなぎの旬」について、天然うなぎと養殖うなぎの違いを解説しました。
「うなぎ=夏」というイメージは根強いですが、実際には天然と養殖では旬の意味が異なります。それぞれの特性を知ることで、より美味しくうなぎを楽しむことができます。
特に重要なポイントは以下の通りです。
- 天然うなぎの旬は秋から冬。冬眠前に脂を蓄えたうなぎは旨みが濃く、身も引き締まっている。
- 養殖うなぎは水温や餌の管理により、年間を通して安定した品質で食べられる。
- 「夏の土用の丑の日に食べる」習慣は、江戸時代の販促から始まった文化的な側面が強い。
- 新仔うなぎは、その年に育った若いうなぎで、やわらかくとろけるような食感が魅力。
「うなぎの旬」とは単に季節だけの問題ではなく、育て方や流通、文化までを含む奥深いテーマです。この記事をきっかけに、次にうなぎを食べるときは、ぜひ“旬”を意識して味わってみてください。